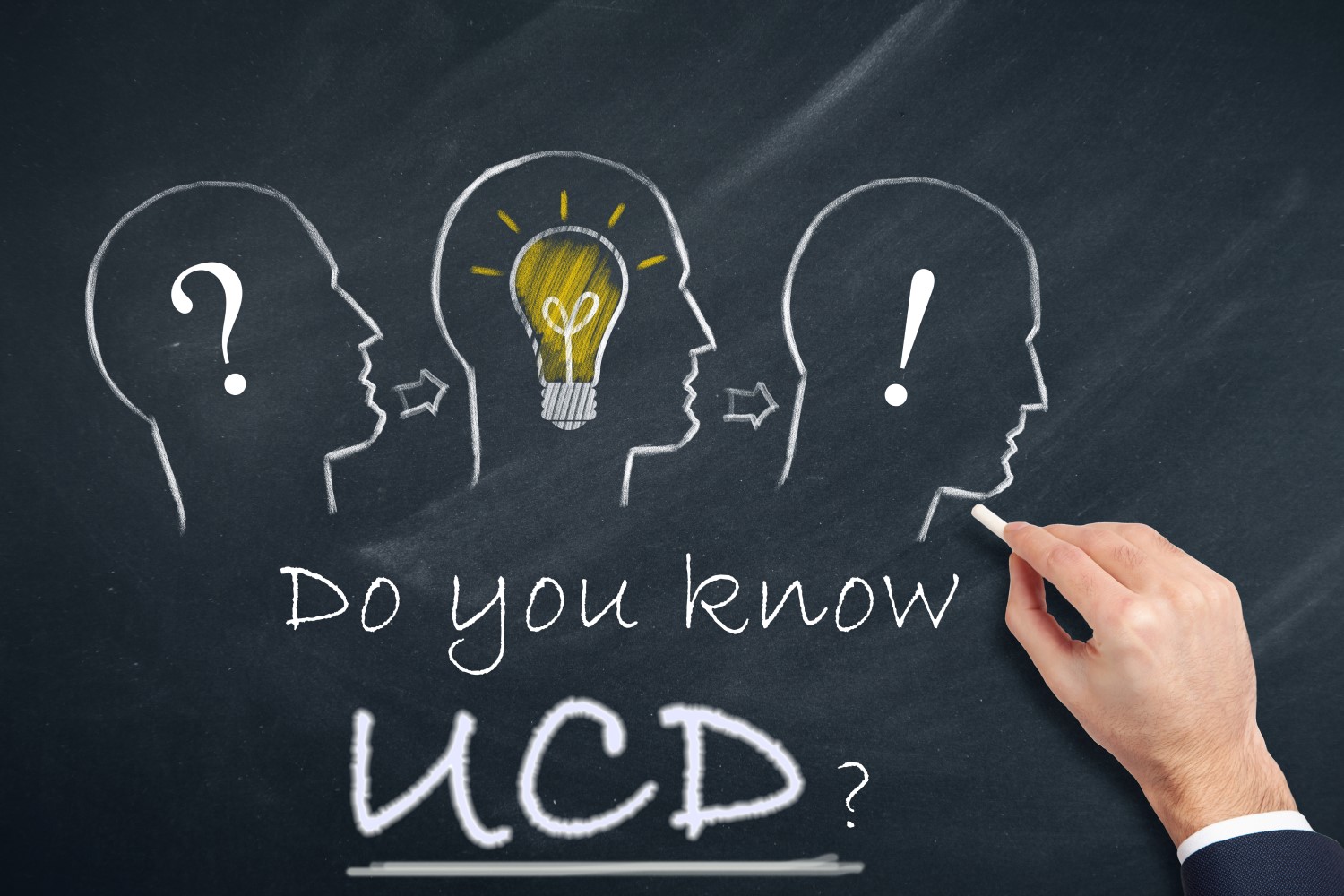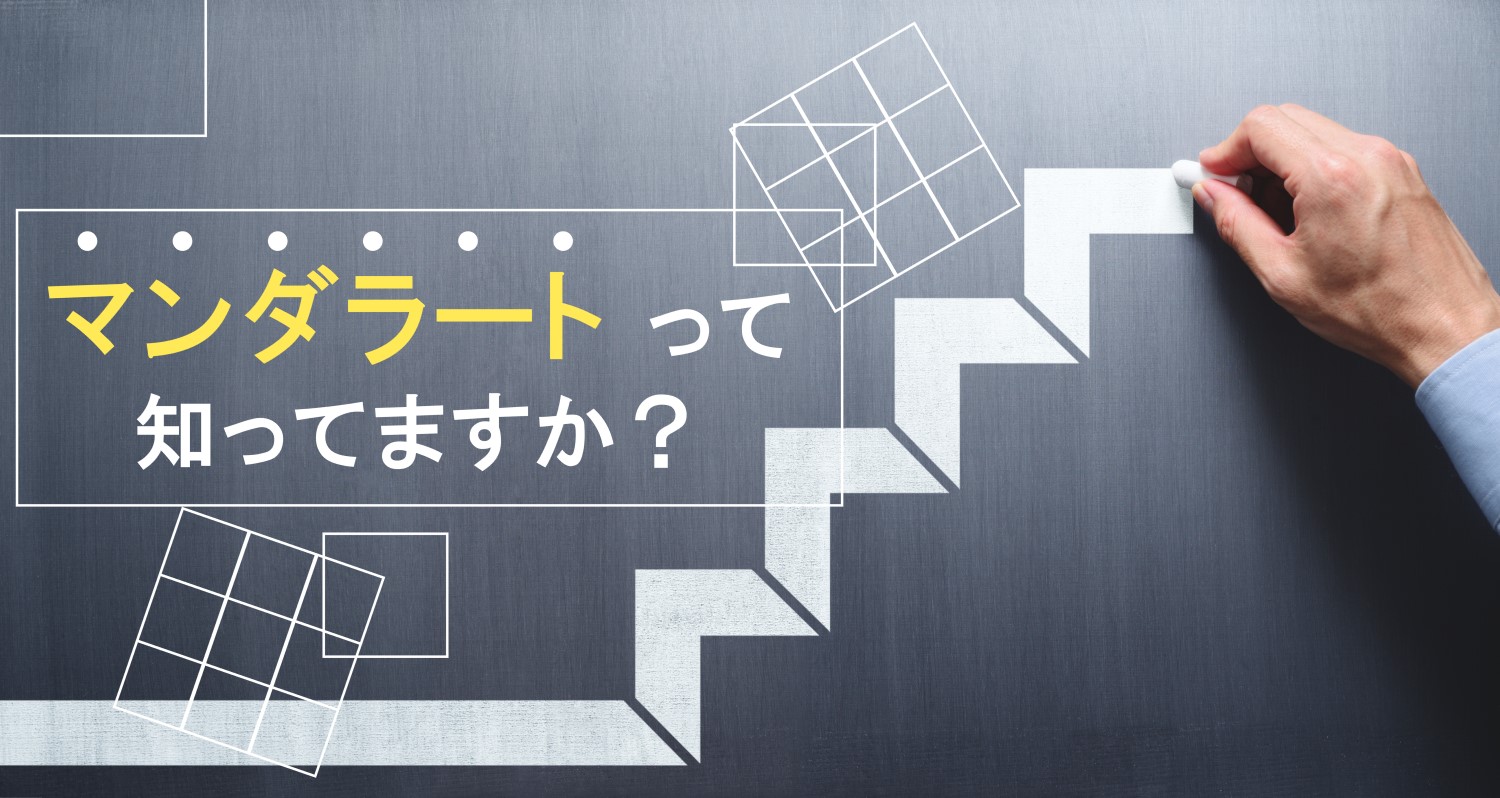保険や税金などのパンフレットや契約書類とか、食品パッケージの原材料やアレルゲンの情報の表記とか、自分の健康とかお金とかを守るための大事な情報にもかかわらず、文字が細かくて何か読みづらいなと感じたことありませんか。
もし読めたとしても表現が難しかったり解説がなかったりして、重要なことなのに頭にすんなり情報が入らない、そのような情報の不便さを解消するために生まれたのが「UCD」です。
今回は情報が伝わらず不便に感じたパターンから、UCDでどう対処できるか紹介します。
情報が分からないお悩み、伝わりづらいお悩み
将来の人生に関わる重要そうなパッケージや書類に限って、分かりづらく書かれてあってどんな内容か分かりにくいもの。
今回は情報の伝わりにくさでお悩みの3人のケースを見てみましょう。
持ち家に暮らすAさんのもとへある日、固定資産税の納税通知書が届きました。しかしAさんはその時「正直、書類が見づらいな」と感じていたようです。
というのも書類の内容が全て薄い青色で小さく印刷されていて、とにかく書面が見にくい。
さらに書面には、固定資産税の合計金額など必要最低限の情報しか明記されておらず、どこをどう読めばいいのか最初は分からず、かなり戸惑っていました。
その後も毎年、納税通知書が来るたび「もう少し見やすくなってほしい」と思っていたようです。
銀行の窓口係として務めるBさんは、来店客の書類に関するこんな意見に悩んでいました。
「どう書けばいいか分かりづらい」「記載が多くて読みながら書くのが面倒だ」
Bさん自身も、来店客一人ひとりに毎回書類の書き方を説明するのが負担に感じていて、顧客も銀行員も書類のレイアウトのせいで無駄にストレスに感じているのではと思っていたようです。
もし書類のデザインを改善できれば、Bさんの店舗だけでなく、銀行の全支店での窓口業務の負担が減らせそうです。
一人暮らしをしている70代のCさんは、ほぼ毎日近所のスーパーやコンビニで食料品を調達しています。
Cさんにはそばアレルギーがあり、調味料や総菜などの加工食品を買うときは、そば粉が含まれていないか表記をくまなくチェックするようにしていました。最近、近所のスーパーがPB商品のパッケージを新しくしたのですが、アレルゲン表示のテキストが小さくなってしまい、Cさんは表示を確認するのに手間取るように。
現在でもアレルギー表記がはっきり確認できる食品だけ買うよう気を付けてますが、PB商品が買えなくなり、買える商品の幅がややせばまって不便に感じるようになりました。
この三人の悩みを解決するには、まずパンフレットやパッケージのデザインそのものを分かりやすい、そして見やすいように改善する必要があります。
分かりやすさを追求した情報デザイン「UCD」
文字情報をより伝わりやすくするには、「UCD(ユニバーサルコミュニケーションデザイン)」というデザインの改善手法を用いるのがおすすめです。UCDは文字情報の伝わりにくさの原因を取り除いて、誰もが容易に情報が伝わりやすいように設計されました。
現在、UCDは一般社団法人ユニバーサルコミュニケーションデザイン協会(UCDA)により運営されています。企業や団体は情報デザインを改善したい対象物をUCDAや、UCDA会員となっている企業に評価・改善してもらうことで、UCDA認証を取得できます。
UCDAによる評価・改善では、DC9ヒューリスティック評価法という特許を取得した方法が用いられます。これは産業・学術・生活者の集合知により「情報量」や「フォントの大きさ」などといった9項目からなる「わかりやすさの9原則」により対象物の情報デザインを評価するもの。
この評価方法により対象物を分析して、問題点を可視化することでどこをどう改善すべきかプランを立てていきます。

UCDの詳細については関連記事も見てくださいね!
まとめ
パンフレットやパッケージが見にくい、分かりにくいという意見が出たら、情報がユーザーに伝わりにくくなってるサイン。そういう場合は、UCDによる情報デザインの改善が効果的です。
UCDはバリアフリーや多言語対応などに比べたらそれほど認知されていないものの、高齢化や外国人の増加などの社会の変化を考慮すると、「誰でも情報がすぐ分かるデザイン」というのはかなり重要ですよね。
UCDがどんなものか興味を持ってくれたら、ぜひほかの記事や当社のサイトなども参考にしてください。
関連リンク
[注1] UCDA協会:「第44回:帳票の見直しが業務改善のきっかけになり、コスト削減を実現しました。」
関連サービス
東洋美術印刷:情報のユニバーサルデザイン